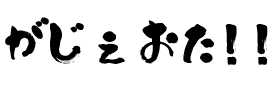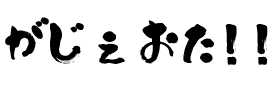OpenAIの動画生成AI「Sora」が初めて公開されたとき、その圧倒的なクオリティに世界中が驚愕しましたよね。物理法則を理解しているかのようなリアルな映像、複雑なプロンプトにも対応するその能力は、まさにゲームチェンジャーでした。
(今はGoogleのVeo3が猛威を振るっていますが)
そんなSoraの次世代モデル「Sora 2」がまもなく登場すると噂されていますが、それに伴い、OpenAIが新たな動きを見せているようです。米国のテックメディア「Engadget」の報道によると、OpenAIはSora 2と連携する、TikTokのようなAI特化型のソーシャルアプリを開発しているとのこと。今回はこの衝撃的なニュースについて、詳細を見ていきましょう。
「AI版TikTok」が登場か?
この新しいソーシャルアプリは、まるでTikTokのように、縦長の動画が次々と流れるフィード形式を採用しているようです。しかし、一つだけ決定的に違う点があります。それは、ユーザーがアップロードした動画や写真ではなく、AIが生成したコンテンツのみが流れるという点です。
Sora 2で生成された動画は、アプリ内で共有され、ユーザーはそれをスワイプして次々と視聴することができます。今のところ、生成できる動画の長さは10秒以内という制限があるようですが、これはサーバーへの負荷を考慮した措置かもしれません。
ユーザーの「似顔絵」も生成可能に?
さらに興味深いのは、このアプリに本人確認機能が搭載されるという噂です。この機能を利用すると、Sora 2はユーザーの「似顔絵」を動画内に生成できるようになるようです。
これは、自分のアバターや分身のようなキャラクターを動画に登場させられるということ。他のユーザーがあなたの「似顔絵」を使った動画を生成し、タグ付けすることも可能になるとのことです。ただし、プライバシー保護の観点から、誰かがあなたの似顔絵を使った動画を生成した場合、たとえ投稿しなかったとしても、あなたに通知が届く安全対策が講じられると報じられています。
なぜOpenAIはソーシャルアプリを開発するのか?
多くの人が疑問に思うのは、なぜOpenAIが動画生成モデルだけでなく、ソーシャルアプリまで手掛けるのか、という点でしょう。Engadgetの記事では、その理由としていくつかの可能性を挙げています。
- AI生成コンテンツのプラットフォームを独占する: ユーザーがSora 2で生成した動画を共有する場を提供することで、他の動画生成AIモデルへのユーザー流出を防ぎ、コミュニティを形成しようという狙いがあるかもしれません。
- AIモデルの学習データ収集: ユーザーが生成したコンテンツやその反応(いいね、コメントなど)は、Sora 2の性能をさらに向上させるための貴重なデータとなります。自社でプラットフォームを運営することで、そのデータを効率的に収集できるという利点があります。
一方で、著作権や安全性に関する課題も指摘されています。OpenAIは著作権で保護されたコンテンツの生成を拒否するとしていますが、その保護がどれほど強固なものになるかは不透明です。
AIによるショート動画のプラットフォームをつくるのはいいんですが、「Italian Brainrot」のような何の意味もないショート動画のたまり場になりそうな予感がするのは自分だけでしょうか。
そうなると、まさに「AI Slop(生成AIの生み出したゴミ)」が溢れるプラットフォームになりそうです。